SES2025は221名の方にご参加いただき,今年も大盛況のうちに終了いたしました.
ご参加いただいた皆様,ありがとうございました.


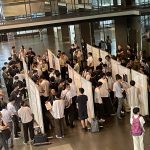




受賞者(敬称略)
最優秀論文賞
- Gradleビルドスクリプトの検証を目的としたテストライブラリの提案
- 藪下 友, 柗本 真佑, 楠本 真二(大阪大学)
- 開発者のIDE操作履歴に基づくソースコード著者推定
- 大森 隆行(静岡大学), 桑原 寛明(南山大学), 西垣 正勝(静岡大学)
研究奨励賞
- 拡張知識を持つLLMシステム向けテストケース生成基盤 TORAK
- 新原 敦介, 竹森 司, 小川 秀人(日立製作所)
- シラバスから見る日本と海外におけるソフトウェア工学教育の違い:世界のトップ大学との比較
- 柏 祐太郎(奈良先端科学技術大学院大学), 近藤 将成(九州大学), 槇原 絵里奈(立命館大学), 亀井 靖高(九州大学)
- 脅威レポートからAIシステムへの攻撃シナリオを生成するLLMベースパイプライン
- 土田 拓将, 藤原 雄矢, 鷲崎 弘宜, 鵜林 尚靖(早稲田大学)
インタラクティブポスター賞
- REST API仕様に基づくLLMを用いた自動バグ修正手法の評価
- 山岸 克紀, 吉田 則裕, 槇原 絵里奈, 井上 克郎 (立命館大学)
- 秩序か混沌か:OpenHandsがもたらすOSSプロジェクトの変化
- 村瀬 巧, 畑 秀明 (信州大学)
- 多版オブジェクト機構による漸進的ソフトウェア移行
- 糟谷 颯希, 田邉 裕大, 増原 英彦 (東京科学大学)
企業ポスター賞
- LLMによる知識グラフ自動構築に基づくアーキテクチャ設計意思決定支援手法の提案
- 森 俊介, 西尾 光平 (早稲田大学),稲川 拓 (デンソー),鷲崎 弘宜,鵜林 尚靖 (早稲田大学)
- ソフトウェア開発プロセスにおける環境影響の実証的評価と考察
- 米原 大樹, 岩塚 卓弥, 山口 央理, 河村 優介 (NTT), 水野 諭孝, 酒井 美代孝 (NTTドコモソリューションズ)
Best International Poster Award
- Identifying Clients Affected by Loss of Backward Compatibility Using Automatically Generated Patterns
- Tomoki Iida (Wakayama University) and Akinori Ihara (Wakayama University)
- Understanding Refactoring in Test Code: An Empirical Study
- Kosei Horikawa (Nara Institute of Science and Technology), Bin Lin (Hangzhou Dianzi University), Yutaro Kashiwa (Nara Institute of Science and Technology), Kenji Fujiwara (Nara Women’s University), Hajimu Iida (Nara Institute of Science and Technology)
- Detecting Machine Learning Design Patterns from Code with Machine Learning Based Approach
- Weitao Pan (Waseda University), Hironori Washizaki (Waseda University), Nobukazu Yoshioka (Waseda University), Naoyasu Ubayashi (Waseda University)
Pick Up!
以下の方々による基調講演・招待講演が決定いたしました.概要およびその他の企画につきましてはプログラムをご覧ください
9月17日(水) 9:45-11:15
平鍋 健児
(株式会社永和システムマネジメント 代表取締役社長)

9月17日(水)13:25-14:55
Daniel German
(ビクトリア大学 教授)

9月17日(水)13:25-14:55
David Moreno
(フアン・カルロス王大学 助教)


シンポジウムの目的
情報処理学会ソフトウェア工学研究会では,1995年度から2003年度にかけオブジェクト指向シンポジウムを開催し,オブジェクト指向技術を中心に研究開発と実践の交流の場を提供してきました.2006年には,ソフトウェアエンジニアリング全般に対する社会的ニーズの高まりに応じるために,シンポジウム名をソフトウェアエンジニアリングシンポジウムと改め,より広い領域の研究者・実務者が集う場として開催しました.同シンポジウムは,その後も毎年実施され,近年における国内最重要なソフトウェアエンジニアリング研究発表の場の一つとなっています.
その間,社会のソフトウェア化が進み,価値創造の源泉がソフトウェアであるという時代を迎えています.そこでは,ソフトウェアの企画,開発,運用,保守,マネジメントおよび周辺の社会インタラクションやピープルを含むあらゆる側面への系統的アプローチとしてのソフトウェアエンジニアリングが果たす役割が大きく,システムが提供する価値の実現手段を与えるという立場から,価値そのものを決定づける立場へと大きな転換を果たしつつあります.
ソフトウェアエンジニアリングシンポジウムでは,論文発表を含むあらゆる活動をビジョンのもとに明確に位置づけ,これまでのシンポジウムの優れたレガシーを受け継ぎながら,今後のソフトウェア工学コミュニティを展望します.ソフトウェアエンジニアリングシンポジウムが具体的に目指すビジョンとコンセプトを以下に示します.
ビジョン
ソフトウェアエンジニアリングのプロフェッショナル集団やそれに連なるアーリーキャリア・学生および周辺の関係者が集い交流するとともに,人々や社会の価値創造に貢献するソフトウェアエンジニアリングに向けた研究,実践および人材育成の成果発表と議論を通じて深化と拡大を進め,その結果を社会へ発信するとともに更なる深化および拡大の基礎を得ます.
コンセプト1「集う」
ソフトウェアエンジニアリングに携わる多様な利害関係者が立場・性別・年代・主張を超えて集い,行動規範をもって相互の理解と交流を深め,連携します.
コンセプト2「研究する」
理論研究にもとづくソフトウェアおよびソフトウェア開発の基本原則の解明や新たなアイディアの創造,事例研究にもとづく実証経験とを突き合わせ,ソフトウェアエンジニアリングの地平を広げつつ,実践へとつなげます.
コンセプト3「実践する」
ソフトウェアエンジニアリングのプラクティスや実践経験を共有および深掘りし,知識,スキル,コンピテンシとして体系化し,ソフトウェア社会における産業発展に貢献するとともに,さらなる研究を促します.
コンセプト4「育成する」
実証済みのソフトウェアエンジニアリング高等教育や職業訓練および組織開発運営成果を共有するとともに,プロフェッショナルが高い倫理感および職業意識を持ち社会的地位を高めることに貢献します.
更新履歴
- スポンサーイベントのページを公開いたしました.
- (2025/09/05)
- 会場・アクセスのページを公開いたしました.
- (2025/09/01)
- 採録論文のページを公開いたしました.
- (2025/08/22)
- 参加募集のページを公開いたしました.
- (2025/08/17)
- プログラムのページを公開いたしました.
- (2025/07/08)
- スポンサー募集のページを公開いたしました.
- (2025/06/23)
- 論文募集,投稿のページを公開いたしました.
- (2025/03/28)
- SES2025のサイトを公開いたしました.
- (2025/01/31)
SES2025の開催形態の詳細
SES2025では,現地参加による研究交流ひいては対話のしやすさも高めるために以下の形態で開催します.
シンポジウム論文,一般論文,既発表・招待論文の各トラック:
- 発表者向け:現地でご発表ください.発表予定者が発表できない状況となった場合は,共著者が代理でご発表ください.
- 聴講者向け:現地でご聴講ください.オンライン配信はありません.
ポスター展示トラック:
- 発表者向け:現地でご発表ください.発表予定者が発表できない状況となった場合は,共著者が代理でご発表ください.
- 聴講者向け:現地でご聴講ください.オンライン配信はありません.
ワークショップ:
- 提案者向け:完全オンライン,ハイブリッド,現地のみのいずれの形態でも開催できますので,提案申込時にお選びください.SES 運営側からは現地会場となる部屋・設備を提供します.
- 参加者向け:討論リーダのご案内に従って,ご参加ください.
開催日程
2025年9月16日(火):スポンサーイベント・ワークショップ
2025年9月17日(水):本会議1
2025年9月18日(木):本会議2
開催場所
早稲田大学 西早稲田キャンパス
主催
共催
IEEE Computer Society Tokyo/Japan Joint Chapter
協賛・後援 (50音順)
重要日程
| シンポジウム論文トラック | 初回投稿締切 | ※延長しません |
|
| 論文更新締切 | ※更新締切までは論文の更新が可能です |
||
| 採録通知 | |||
| 最終原稿締切 | |||
| 一般論文トラック | 発表申込 | ※論文タイトルと概要が必要です |
|
| 投稿締切 | ※投稿論文が最終原稿となります |
||
| 既発表論文トラック | 発表申込 | ||
| 採否通知 | |||
| ポスター展示トラック | ポスター論文あり | 投稿締切 | |
| 採否通知 | |||
| 最終原稿締切 | |||
| ポスター論文なし | 申込締切 | ||
| 採否通知 | |||
| ワークショップ討論テーマ提案 | 提案締切 | ||
| 連動特集号「ソフトウェア工学」特集号 | 投稿締切 | ||




